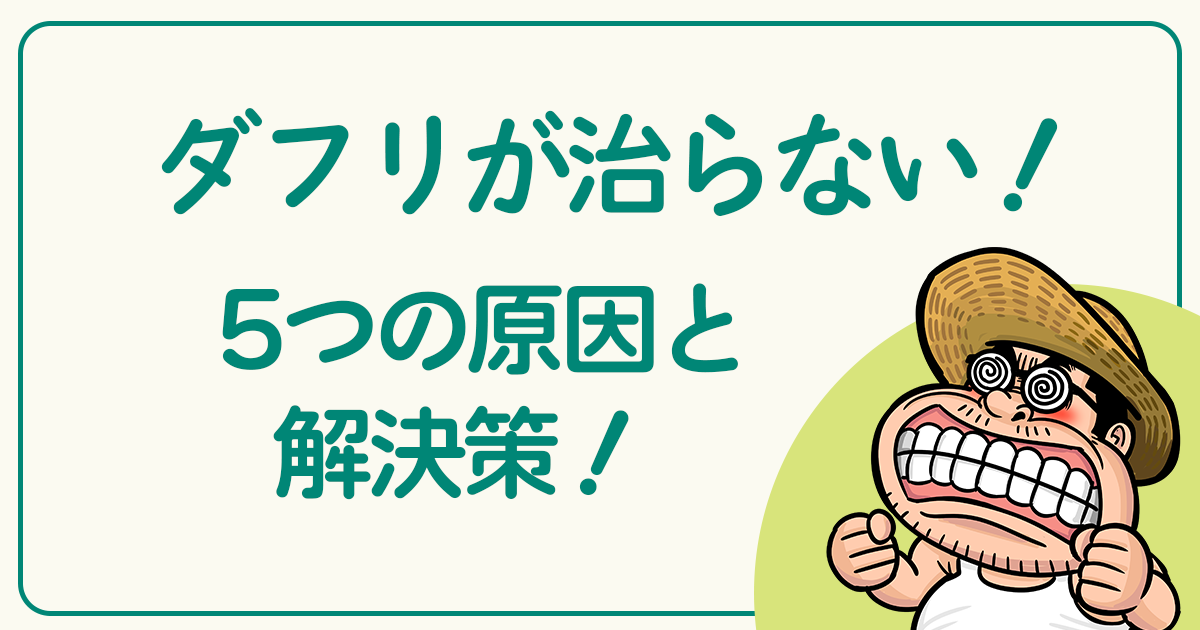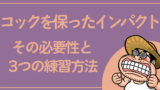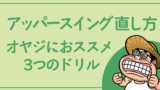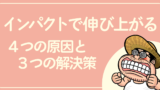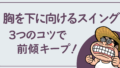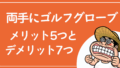まいど!
おやじのゴルフマガジン編集長の「たいしょー」です。
何をやってもダフリが治らない…。
お気持ちお察しいたします。
でも安心してください。
ダフリで悩んだことがない人なんていませんから、たぶん。
そのくらい「ダフリ」というのは国民的ミスと言えるのです。
そんなメジャーなミスなら、解決方法もゴマンとあるはずです。
今回は、私が考えるダフリの主な原因を5つ。
そして、私が最も効果が高いと思う、ダフリ矯正ドリルを1つご紹介いたしましょう。
お時間のあるかたは、ぜひお立ち寄りください!
ダフリが治らない原因
まずはダフリが治らない原因についてです。
これは挙げたらキリがないくらい、たくさんの要因が考えられます。
ここではあくまで私の主観になりますが、代表的なダフリの要因を5つご紹介させていただくことにしましょう。
インパクトでコックがほどける
結果的に、この「インパクトでコックがほどける」からダフることが最も多いです。
「結果的に」というのは、コックがほどけるという症状になるまでの原因も多数あるからです。
これから紹介する他の原因も、結局は「コックがほどけること」によってダフリにつながっているのです。
コックがほどけるとは、アドレスで作ったクラブと腕の角度がインパクトで伸びてしまうことをいいます。
ここが伸びてしまうと、クラブのライ角が大きくなってトゥーダウン現象が起こってしまうのです。
ただでさえ、ゴルフスイングはダウンスイングのシャフトのしなりによってトゥーダウンが起こります。
それに加えて手首でもトゥーダウンを作ってしまっては、さらにクラブヘッドはボールの手前に落ちやすくなってしまうということですね。
右肩が下がる
ダウンスイングからインパクトにかけて、右肩が大きく下がるとダフリやすくなります。
「あおり打ち」とか「かっち上げスイング」とか言われるやつですね。
「ボールを上げたい」という気持ちが強いと、アッパースイングが強くなります。
そうするとクラブ軌道の最下点が、ボールの手前に来やすくなるのです。
伸び上がる
切り返しからインパクトで体が伸び上がるのも、ダフリにつながる大きな要因です。
インパクトで体が起き上がってしまうと何故ダフるのか?
それは最初に紹介した「コックがほどける」ようになってしまうからなのです。
アドレス時よりも、インパクト時の前傾角度や手元が高くなる。
そのままではクラブがボールに届かなくなる。
すると本能的に手首のコックをほどいて、クラブを長くするように調節してしまう。
これが伸び上がりによってコックがほどける流れですね。
上体が開く
インパクトでの上体の開きが早くてもダフリやすくなります。
インパクトで上体が開くと、左へスウェーしたり、右肩が下がりやすくなります。
これらは全て「コックのほどけ」につながります。
あまり上体のクローズを意識しすぎても、体の回転が止まって逆にダフリやすくなってしまいます。
手元の通り道をしっかり確保できるように、スムーズな体の回転と腕の振りを同調させる必要があるのです。
ゴルフって、本当に難しいスポーツですね…。
インパクトでボールを凝視してしまう
「ボールをよく見ろ!」
と、昔からまことしやかに言われてきました。
私はこの言葉には少々懐疑的です。
だってディンプルのひとつひとつが分かるくらい凝視してしまうと、体の回転が止まりやすくなるから。
ボールを良く見ようとして、トップから頭が突っ込んでしまう人もいます。
これらは間違いなくダフリの原因になります。
スイング中のボールは、何となくぼんやりと見るようにしましょう。
ダフリを治す最も効果的な練習方法
ご自分のスイングがダフリやすいかどうかを判断するには、「ヒザ立ち打ちドリル」が最も有効ではないでしょうか。
K155
L155
このドリルでは、
左にスウェーができません。
右肩が少しでも下がるとダフリます。
そしてこのドリルでは、もうひとつ大きなスキルを手に入れることができます。
それはアームローテーションの習得です。
ダフリやすい人は、アームローテーションが上手く使えていない人が多いです。
最近よく言われる「手を使わないで体のターンで打て」というのは、もともと腕を使える人に対する言葉と思っています。
基本的なクラブの振り方を身に付けていない人に、「腕を使うな」なんて言ったらスイングになりませんからね。
そんな方には、この練習方法を試してみてください。
これこそ、ダフリにつながる多くの要素を矯正してくれる万能ドリルなのです。
中級者以上限定のスパルタ練習方法
さて、最後に少し「おふざけ的」な練習方法を2つご紹介して終わりにいたします。
どちらも私が過去にやったドリルなのですが、それぞれ別の意味でリスクが高いです。
決してお勧めするわけではありませんので、余興の読み物として捉えていただければ幸いです。
ベアグラウンドの上から打つ
これは本当によくやりました。
昔は、1階打席が土の上から打てる練習場があったんです。
土を固めた上に、スタンス用の黒いゴムマットと、ボールを置く長方形の緑のマットが置いてあるだけ。
その緑のマットをどけてしまえば、その下は固い土のライになっているのです。
つまりはベアグランド。
ここでのダフリは一発で分かります。
マットのように滑ってくれませんからね。
極端に飛ばなかったり、手に強い衝撃が来たり…。
だから必死になってダフらない打ち方を覚えようとしたものです。
そしてベアグランドから「良い入り」をしたときは、何とも言えない心地良さを味わえたのです。
なので、練習場のライがとなってくれたのですね。
現代の練習場は近代化されているので、よっぽど地方でも行かない限り、こんな昭和チックな施設はないでしょう。
だから問題ないとは思いますが、決してお勧めするものではありません。
このようなリスクを伴いますので、もし試される方は自己責任でお願いいたします!
ボールの手前に10円玉を置いて打つ
こちらは、たま~にやりました(笑)
ボールの15㎝ほど飛球線後方に10円玉を置くのです。
遥か手前をダフってしまったら…。
もちろん10円玉は、ボールと一緒に飛んでいってしまいます。
仲間同士でヒートアップしてくると、これが途中から100円玉になったりします。
これは正直シビれます…。
先ほどのベアグランド練習は、体やクラブにダメージのリスクがありました。
どちらかと言うと10円玉練習は、財布へのダメージのリスクですね。
これも昔だからできた遊びです。
今やったら練習場から出禁を食らうので、絶対やらないでくださいね!
まとめ
今回は、ダフリが治らない5つの原因と、ダフリを解消する3つの練習方法をご紹介させていただきました。
とはいえ、最後の2つは番外編となります^^
ぜひぜひ、安全第一の練習ドリルを実践してくださいね!